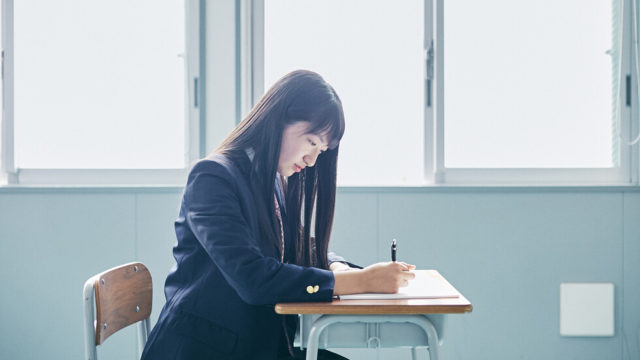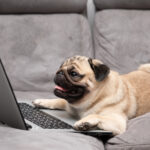高校生が不登校になると将来ヤバいのではないか?と思う人も多いでしょう。
実際は不利な点もいくつかありますが、だからと言って人生が終わるということではないです。
不利な点は、留年の可能性が高いことや、大学受験の際に学力の差がでることが考えられます。しかし、不登校という環境が自分のやりたいことを見つけるチャンスにもなります。
不登校の原因は学業不振、友人関係の悩み、不安などによるものが多いです。親は子供がどのような理由で不登校になったかを把握することが大事でしょう。
親がすべき対応は初期段階では学校に行くことを急かしたりしないようにしましょう。また、長期的な考え方では学校以外での学習方法を一緒に考えることが必要でしょう。
高校生の不登校はヤバいのか?考えられる影響は?
高校生で不登校になってしまうと将来はヤバいのでしょうか?
この質問に対して、簡単に言うなら「ヤバいこともあるし、ヤバくないこともある」と言えるでしょう。
この記事では、もっと詳しく不登校であるメリット・デメリットを解説しています。最後まで目を通して、今の現状を把握し、これから必要な行動をしていきましょう。
不登校で人生が終わる、ということはない
声を大にして言いたいことは、「不登校だからと言って人生が終わる」ということではないです。これは先ほど述べた、「高校生で不登校はヤバくない」ということを表します。
なぜ、人生が終わりではないかというと、今後の生き方次第で人生はどうにでもなるからです。今後の生き方に”高校生の時の不登校だった”という事実はそこまで関係ありません。
最近では、”人生100年時代”と言われるほどで、高校生後の方が、より長い人生を過ごすことになります。
ライブドア代表取締役社長CEOであるホリエモンこと堀江貴文さんは、多くのメディアで「勉強ができることは人生に関係ない」、「学校に行くメリットはなく、自分の好きなことをする方が大切」と述べるくらいです。
大切なことは、今、”不登校である事実”があっても、今後の生き方次第でそれを乗り越えられる可能性が沢山あるということです。
ただし、不利になる点もあることは理解しておくべき
高校生不登校で人生が終わるわけではないと言いましたが、不利になる点もあることは理解しておきましょう。
不利になる理由は、高校に在籍していると、その学校のルールに縛られてしまうからです。それぞれ高校には、生徒の学習状況や生活態度を見て、次の学年に進級できる・できないを決めなくてはいけない一種のルールがあります。
その点でいうと、不登校というのはどうしても不利になってしまうでしょう。また、高校卒業後の進路で大学に進む場合、大学受験が不利になると言えるでしょう。
以下では進級・留年や大学受験において不利になるパターンを解説しています。
①全日制の高校の場合留年の可能性が高い
全日制の高校に在籍して不登校の場合、留年する可能性が高くなります。
留年する可能性はどこから生まれるかというと、先ほど少し説明した学習状況・生活態度から判断します。
どの全日制高校も、年間で受けなければいけない授業時間数は決まっています。その授業時間数を下回っている場合、残念ながら”進級不可=留年”となってしまいます。
ちなみに、授業時間数は文部科学省から目安の授業時間数が与えられており、各学校ごとに時間数を定めるようになっています。
例えば、国語だと3年間で授業時間は315時間ほど、年間で105時間づつ設定するようになっています。
では、具体的に年間で受けなければいけない授業時間数はどのくらいなのでしょうか?
3分1以上の欠席で単位を落とす
全日制高校では3分の1以上の欠席で単位を落とす=留年になることが多いです。
高校ごとに各教科ごとの授業時間数は決まっているという話をしました。その時間数の3分の1を欠席した場合、留年になるというルールがあります。
例えば、先ほどの国語の授業時間数の話をすると
- 年間授業時間数を140時間とする
- 3分の1以上の欠席で単位を落とす
→年間46時間以上休んでしまうと単位を落とす=留年になるという計算になります。
欠席日数は一概に3分の1というわけではなく、高校によっては4分の1、5分の1欠席のところもあります。これは高校ごとに規則が違うので気を付けなくてはいけません。
現在、不登校だという方は、まず学校に聞いてみるのがいいでしょう。
②留年になると中退を選ぶ可能性が高い
不登校者は、留年になると必然的に中退を選ぶケースが多くなります。
そもそも留年は当該学年の科目を再び履修しなおすという意味です。つまり、昨年の学年に残るということになります。
不登校の生徒は長期欠席が多いことから最低出席日数が足りず、留年になるケースが多いです。そして、留年からそのまま中退をしてしまうケースが大変多いです。
つまり、このまま留年しても現状を変えられないと判断した結果です。
統計では5人に1人は中退を選択
統計では高校生で不登校の約5人に1人は中退を選択しています。
文部科学省「令和2年 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると不登校生徒の中途退学者は19.7%になっています。
不登校の問題が完結していない状態で、留年という状態になると、やるべきことが多く、より時間と労力を使うでしょう。
③学力がない場合、大学受験が不利になる
大学受験を考えている場合、学力がないという面で不利になる場合があります。
不登校になり学校へ登校ができないと、学力が低下するパターンが多くなります。高校というのは授業の難易度も上がるので、なかなか自学学習で何とかなるものではありません。
基本的に学校へ通っている生徒と不登校の生徒を比べた場合、学力の差があるのは仕方のないことでしょう。
大学受験も然りで、高校での学習内容を応用した問題が出題されやすいこともあり、圧倒的に不登校であると受験に不利になります。
どうしても学校に登校できない高校生へのアドバイス
不登校だと不利な面がいくつかあるのがわかりました。これを見てがっかりした方や、これからが不安になった方もいると思います。
ですが、冒頭で述べたように不利な面はあるにせよ、人生が終わったわけではないことを思い出しましょう。これからの行動次第で人生はどうにでもなることを胸に刻んでください。
以下はどうしても学校に登校できない高校生へのアドバイスです。
自分のしたいことを見つけるチャンス
不登校はピンチではなく、自分のしたいことを見つけるチャンスです。
なぜなら、不登校だと自分を見つめる時間がたくさんあるからです。自分の趣味に没頭したり、時間がある分、やりたいことを発見できるチャンスが沢山あります。
不登校の生徒がゲームが好きで、E-Sportというオンラインゲームスポーツで生計をたてる立派な職業についている方も多くいます。
他にも、クリエイターやブロガー、自然が好きな方はアクティブな方面へと進む方もいます。
つまり、不登校は学校という環境を外れるからこそ別の景色を見ることができます。不登校をマイナスに感じるのではなく、プラスに変換して「自分が本当にしたいこと」を見つけると良いでしょう。
挫折は人生に付き物
人生に挫折は付き物だということを理解しましょう。不登校になった原因は様々ですが、その中に高校生になって大きな挫折を味わったケースがあります。
例えば、勉強でうまく結果が出ない。スポーツの部活動で実力差ありすぎて到底適わない。などがあります。
中学生までは横一線だったものが、高校生になると身体的な成長などで、実力差が顕著に出てしまうことがあります。初めての挫折を経験して、心が折れてしまう方も少なくありません。
ですがアドバイスとして、”長い人生において挫折は誰しもが経験するもの”です。なので、今経験した挫折は、長い目でみると大したことはないと思えるでしょう。
高校生が不登校になる原因は主に5つ
令和2年の公立全日制高校では、不登校者数は20,981人います。
そして、不登校には様々な原因が考えられます。しかしながら、割合が多い理由もあるので、今回は5つ紹介します。
特に親は、不登校の理由を把握していないことがよくあります。それは、子供自身が何で悩んでいるか・理由を親に言わないことがあるからです。
思春期の子供にとって、なぜ学校へいけないのかを伝えるのは恥ずかしさや、プライドもあるのでしょう。
なので、これから紹介する5つの原因を参考にして、自分の子供がどの原因で不登校なのかを考えるきっかけになればいいと思います。
文部科学省「令和2年 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
①学業不振
一つ目は学業不振が原因と考えられます。統計データによると1,634人、7.8%の不登校者が高校での勉強についていけない理由で不登校になっています。
原因は中学校の学習内容に比べ、高校は内容が高度化するからでしょう。基礎的な内容は中学校で学び、土台ができて初めて高校での発展内容がわかるようになります。
なので、中学校の内容があやふやな人や、高校での授業についていくだけで精一杯な人は学業不振に陥りやすいです。
また、高校は偏差値が同じくらいの生徒が集まります。今まで高得点や、評定が良かった人が今までと同じような成績をとれなくなるケースも多くなります。
②漠然とした将来への不安
二つ目は漠然とした将来の不安が原因です。将来の不安には進路に関わることも含まれ、統計では1,299人 6.2%の生徒が不登校になっています。
漠然とした不安とは、「高校卒業後はどうすればいいんだろう。」「自分は会社で働けるのか。」「社会人って大変なんだろうか。」のような悩みが多いです。
「そんなことが原因で不登校になるの?」と思う方も多いでしょうが、学生にはよくあるケースです。
このような漠然とした将来の不安は”無気力”という症状になりやすいです。
そして、”何に対しても無気力”になってしまう生徒は、統計ではなんと35.3%もいることがわかっています。
③人間関係での悩み
3つ目は人間関係での悩みによるものです。これはいじめに発展するケースだけではなく、友人関係をめぐる問題も含まれます。
高校生になると
- 部活動
- スマホでのやりとり
- 友達と受験勉強
- 恋愛関係
- 学校終わりのアルバイト
などで、人間関係が絡む機会が多くなります。特に今では、SNSが絡んだ、人間関係の悩みやトラブルが原因で不登校になるケースが多いです。
④今までにない挫折経験
4つ目は、今までにない挫折経験が原因になるものです。先ほど、高校生活では挫折経験が増えるだろうという話をしました。
挫折経験は大きく2つのパターンに分けられます。
- 学業での挫折
- 学業以外での挫折
です
学業での挫折
学業での挫折は何度も説明しているように、高校での学習についていけなかった。成績が思うようにでない、周りにどんどん抜かされるなどがあるでしょう。
よくあるケースで、元々の自分のレベルよりも、高いレベルの進学校へ入学した生徒に多いです。
高校受験は努力が実り入学できたものの、あまりにもレベルが高く、授業についていくのも一苦労という生徒は挫折を経験しやすいでしょう。
学業以外での挫折
学業以外の挫折は部活動・クラブ活動があげられます。
高校生にもなると、その部活動やクラブでトップレベルになるような人たちもでてきます。その方たちと比べて実力差を感じてしまう人や、努力だけではどうにもならないと感じて挫折してしまう方は多いです。
⑤あそびや非行
最後の原因は、あそびや非行によるものです。夜遊びやタバコ・飲酒などから高校に通う頻度が少なくなり不登校になるケースです。
統計によると13.1%で2,748人もの生徒が不登校になっています。
親がすべき不登校の子供への対応
親がすべき不登校生徒への対応は初期対応と長期的な対応によって変わってきます。
初期対応は以下の対応が必要です。
- 不登校関係なく今まで通り接する
- 学校へ行くことを急かさない
そして長期対応は次の通りです。
- 登校以外の学習方法を勧める
- 家庭外で相談・協力してもらうところを探す
では、それぞれ具体的にどのような行動が必要か見ていきましょう。
【内部リンク】高校生の子が不登校になった場合、親の反応はどうする?心がけたい接し方を紹介
初期対応として適切な行動は?
初期対応に適切な対応は①不登校関係なく今まで通り接する②学校へ行くことを急かさないの2つを徹底しましょう。
初期対応は、子供と親の関係性を決める大事な行動になるのでとても大切です。親がよくやりがちなミスが初期対応には多いので必ず目を通すようにしましょう。
不登校関係なく今まで通り接する
初期対応は不登校に関係なく今まで通り接してあげましょう。「今まで通りに接するなんて当たりまえ」と思われがちですが、実はそんなことはありません。
子供が不登校になると、どうしても腫れものをさわるかのように不登校であることを変に避けたり、優しくしたり、もしくは反対に厳しく接して学校に行かせようと無理強いしたりする親が多いです。
そうではなく、不登校という事実を除いて、”一人の息子・娘”として接してあげましょう。要は、今までと変わりなく接してあげれば良いです。
子供は不登校になったことを親がどう思っているかを気にしているものです。「ダメな子」と思われたらどうしようと感じている子もいます。
今まで通り接してあげると、子供も「不登校だけど、変わらず接してくれるんだ」と思うはずです。
まずは、態度を変えずに接していくことで親子の関係性を深めていきましょう。親子関係が良好な場合、不登校の解決はスムーズにいきやすいからです。
子供は特別扱い・気を使われるのはイヤ
子供は特別扱いされたり、気を使われるのはイヤなのを知っておくと良いでしょう。特に親にそのような接し方をされると子供は拒否反応を示します。
子供は大人よりも感受性が豊かだと言われています。この人は本音で話をしてくれているのか、そうではないかは一発でお見通しです。
そして、子供からの評価は一度ついてしまうと、それを変えるまで時間が掛かります。なので、初期対応はミスをしやすく、大事な対応です。
学校へ行くことを急かさない
二つ目に大事な初期対応は”学校行くことを急かさない”ことです。
親がやりがちなミスで一番多いのが、本人の気持ちを無視して学校へ行かせようとすることです。この行動は全くの逆効果になるのでしないようにしましょう。
不登校から回復の状態に入ると、自分から学校に行ってみようと思ったり、前向きな行動が増えてきます。親は子供の行動意欲が出てくるまで待つことが肝心です。
子供のしたいことを優先する
“子供の行動意欲が出てくるまで待つことが肝心”とお伝えしましたが、言い換えると子供のしたいことを優先することが大切です。
不登校の状態になると自分の求めるものを提示されると拒否したり、自分の殻にこもってしまうケースがあります。なので、初期対応としては子供が「何かをしたい」と意思表示したものを率先してやらしてあげましょう。
「それでは子供がわがままになってしまう。」と思う親も多いと思います。しかし、もし子供がわがままになってしまうなら、それは、不登校以前の家庭内の教育が原因だったりします。
回復期までは3カ月~1年はかかることを理解する
不登校の回復期までは3カ月~1年はかかることを頭に入れておきましょう。
そもそも、回復期とは子供が”自分から何かをしたい”などの意欲や興味がでる期間のことを言います。不登校の状態が回復して登校できる期間ではないので間違わないようにしましょう。
子供の意欲や興味が出るまで、早くても3カ月は掛かります。つまり、それより前の期間は不登校の状態から進展することは難しいと考えましょう。
なので、学校へ行くことを急かすことなど言語道断となるわけです。不登校の問題はどの学年でも辛抱強く待つことが解決のカギになるので覚えておきましょう。
長期的に備えておきたいマインドや対応は?
では、次に長期的に備えておきたいマインドや対応の仕方を紹介します。
具体的には①登校以外の学習方法を勧める②家庭外で相談・協力してもらうところを探すことが重要です。
登校以外の学習方法を勧める
長期的な目でみると、登校以外の学習方法を勧めることも必要です。
高校生の不登校だと、高校卒業後の進路を決めるうえで勉強を行わなくてはいけない状況が大きいです。どうしても学習はどこかのタイミングで必要になってくるでしょう。
学校に登校することが全てではないので、場合によっては登校以外の学習方法を提示してあげると子供の為になります。
気を付けたいポイントは、先述した通り、子供の意欲や関心が学習に向いてきてから話を勧めることです。
子供の回復期以外に学習の話をしても、話が進まないうえに、せっかくの親子関係が悪化する可能性があります。
あくまで、子供の学習する気持ちが出てきてからです。
①タブレット学習
登校以外の学習方法にタブレット学習があります。
タブレット学習はタブレットやスマートフォンの画面越しに各教科の授業を閲覧して学習する方法です。不登校生徒だけでなく、大学受験の為に活用している生徒も沢山います。メリットは以下の通りです。
多くの学習塾がタブレット学習プランを提供しているので、気になる方は各HPを参考にするといいでしょう。
②家庭教師(オンライン学習も)
家庭教師と学習することも不登校生徒には向いています。
家庭教師のメリットは以下の通りです。
家庭教師は不登校生徒との相性がいいでしょう。理由は先生と頼れる大人のいいとこを集めている傾向があるからです。
最近では、高校生と年齢が近い大学生などの家庭教師も多いです。学習を手助けするのはもちろん、生活の悩みを聞いてくれる方もいらっしゃいます。
③フリースクール
フリースクールに通うのも検討すると良いでしょう。
フリースクールとはNPO法人や、企業によって運営される施設です。学習以外にも遊びを取り入れているスクールもあります。施設によって方針は様々ですので、事前に調べることが必要になります。
家庭外で相談・協力してもらうところを探す
家庭内だけで不登校問題を解決するのではなく、家庭外に相談・協力してもらうところを探しましょう。
どうしても家庭内で不登校を解決しようとするケースが多いですが、その場合ストレスを溜めすぎたり、疲れてしまう場合があります。
また、不登校の問題を解決するには外部の協力は非常に大事になります。不登校問題を専門とする方たちも多くいるので以下を頼りにしてみましょう。
①学校の先生に相談する
②スクールカウンセラーに相談する
③家庭教師などの外部学習を活用する
①学校の先生に相談する
不登校問題は一番に学校の先生に相談しましょう。学校の先生は教育のプロと言えます。子供接し方や、不登校生徒に対してのアプローチ、進路など幅広く知識を持っているでしょう。
まずは、担任や学年主任への相談をしてみましょう。家庭での悩みを打ち明けるだけでも親の疲れもなくなります。
②スクールカウンセラーに相談する
大体の学校にはスクールカウンセラーが勤務しています。スクールカウンセラーは心に悩みがある生徒や不登校になった生徒とカウンセリングして問題を解決する役割です。
スクールカウンセラーは話を聞くということに長けているので、不登校生徒とのコミュニケーションに非常にうまく行えます。
生徒だけではなく、親とのカウンセリングも大切にしています。自分一人で悩むのではなく、専門家に話を聞いてもらうだけでも違うでしょう。
高校生が不登校の場合は編入も視野に入れる
現在通っている学校で不登校への解決が難しいと判断した場合は、他の学校へ編入することも視野に入れましょう。
具体的には全日制高校への編入か通信高校への編入をオススメします。それぞれメリットが違うので、最後まで目を通してみてください。
全日制高校への編入
全日制高校への編入をするのが選択肢の一つです。
ただし、編入に際しては編入試験を受けなければ行けない学校がほとんどですので、ある程度の準備が必要になります。編入を希望する場合は、計画的に期間を設けることも必要です。
また、今いる学校を退学するのではなく籍をおくことが重要です。
前校の単位を引き継げるので安心
今いる学校へ籍をおく理由は、前校の単位を引き継ぐことができるからです。
転校という形をとれば、原則すでに取得した単位は引き継ぐことができるので、また一から始める必要はありません。
必ず編入先の学校に単位についての話を聞いておきましょう。
通信高校への編入
もう一つの編入先は通信高校です。通信高校は編入試験はないところがほとんどですので、希望をすれば入ることができます。
通信高校はオンライン学習がほとんどで、通学は少ないのがポイントです。
自分のペースで学習できる
通信高校は自分のペースで学習がすすめられます。
定められた単位を取得すれば卒業できるので、時間で区切られることはありません。自分の好きなタイミングに学習をすすめられるので、全日制高校の様式が合わなかった生徒には良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?高校生が不登校だからと言って、人生が終わってしまうと考える必要はありません。
留年や大学受験の心配はありますが、それよりも不登校の根本の問題を解決することが最優先です。それには親の対応や接し方も大事になってきます。
問題が解決してくると、自然と登校の回数も増えてくるので留年の可能性も少なくなります。
まずは、子供の不登校の状態を把握し、適切な対応をしたり、頼れる機関と協力しながら子供を支えていきましょう。